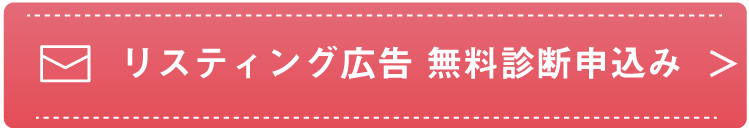メルマガなんて読まれていないと思っていませんか?メルマガを効果的に配信する方法

メルマガをうまく活用できていますか?
メールマガジン(以下、メルマガ)はお客様との継続的な接触を図るための有効なツールの1つです。
「今はメールじゃなくて、LINEでしょ?」とよく聞かれますが、これはターゲットとするお客様次第です。
個人なのか法人なのか、年齢層はどれくらいか、保守的なタイプなのか革新的なタイプなのか、また商材の価格帯はどれくらいか、などによってお客様との最適なコミュニケーションのあり方は異なります。場合によっては、メルマガでもなく紙媒体や、FAXが有効な場合もあり得ます。
いずれにしても、コミュニケーションは「数」がとても大事です。何らかの形でお客様と継続的に繋がりつづけるためのツールを最低1つは用意しておきたいところです。
今回は、メルマガを例に話を進めますが、そのままLINEや紙の通信などにも応用できる考え方です。
メルマガなんて読まれていないと思っていませんか?
「メルマガは一応発行しているけど…実際のところほとんど見られていないのでは?自分自身もほぼ見てないし…」という意見もあります。
実際、各社がこぞってメルマガを配信するようになり、中には望んでもいないのに送られてくるものも少なくありません。その結果、メールボックスには大量のメルマガが届くようになり、うんざりしている人もいるでしょう。
かくいう私も、メールボックスの中には1万件以上の未読メールが溜まっています。
私たちは無意識のうちに情報を取捨選択しており、それはメルマガでも同じです。メルマガが読まれないのは、「自分にとって関係ない」「興味ない」「どうでもいい」と思われているから。
逆に、なにか心に引っかかるものがあれば、お客様は読むし、反応します。
実際に私が見た二つの事例をご紹介します。
事例① 痛恨のミスで大量のクレーム発生
企業Aでは、週に1回メルマガを3万人の人に向けて配信していました。3万人に送っても反応はごくわずか。リンクを貼っているウェブサイトに、配信数に対して0.5~1%ほどのアクセスがある程度でした。もちろん、メルマガに対しての返信などもありません。
なので送っている担当者は、メルマガなんてほとんど読まれていないと考えていました。
そんなある日、担当者は痛恨のミスをしてしまいました。メールの冒頭につけるお客様名に敬称をつけ忘れてしまったのです。つまり・・・
———————-
佐藤様
こんにちは!株式会社●●です!
———————-
となるべきところが、
———————-
佐藤
こんにちは!株式会社●●です!
———————-
と送信されてしまったのです。
すると、呼び捨てにされて気分を害された方々から、大量のクレームメールが送られてきました。そして配信停止の嵐…
担当者にとっては大惨事ですが、私は当事者ではなかったのでその様子を客観的に見ることができました。
そして、「普段は何の反応もないのに、今回はこんなに反応があった。心に引っかかるものがあれば、お客様は気づくんだ」ということを確信しました。
事例② 宣伝を一切やめたらお客様との信頼関係が深まった
企業Bは、コロナ禍による業績不振に苦しんでいました。なんとか挽回しようと、メルマガの配信回数を増やし、自社の商品を積極的にお客様にアピールしていました。
ところが、お客様の反応は期待と真逆。突然大量に送られているメルマガに嫌気がさし、配信停止される方が激増したのです。
そこで、全く逆の発想で、「一切宣伝しないメルマガ」を送るようになりました。
お客様にとって役に立つ内容だけで構成し、商品名も書かず、商品リンクも貼りません。その代わり、毎日配信しました。
すると、徐々にお客様から好意的な反応が寄せられるようになりました。メルマガに対して、わざわざ感想を送ってくださる方が日に10人以上も出るようになったのです。それも、毎日です。
システムトラブルでメルマガが配信できなかった日には、「届いていません」「もう一度送ってもらえませんか?」という催促の連絡が押し寄せました。
それまで10年以上メルマガを配信してきたそうですが、そんなことは初めてだったそうです。
結局、商品の宣伝は何一つしていないにも関わらず、そのメルマガをきっかけにお客様との信頼関係が深まり、お問合せや、他のお客様のご紹介にも繋がりました。
メルマガは、宣伝広告ではなくメディアと捉える
メルマガを意味のあるものにするために大事な考え方があります。それはメルマガを「メディア」と捉えること。
読まれていない、また期待する効果を上げられていないメルマガの大半は「会社都合」「自分都合」で送られています。商品の宣伝をしたいという意図がだだ漏れで、お客様にとっての読む意義を提供できていません。
逆に、このご時世でも読まれるメルマガは、お客様が「読みたい」と思うものです。中にはお金を払ってメルマガを購読している人もいます。
読み手にとって価値のある情報を提供しようと思えば、自社の商品の話や、担当者のプライベートな話ばかりをしている余裕はないはずです。
メディアとしてのメルマガ。配信までの3ステップ
メディアとしてメルマガを配信していくための簡単な3つのステップをご紹介します。
①ターゲットを明確にする
自社のことを知っている人/知らない人、商品を買ったことがある人/ない人、など送る先によって求める情報も前提知識も変わってきます。自分はこれから誰に対して情報を届けようとしているのかを明確にしましょう。
②ターゲットが知りたいことを知る
ターゲットが明確になったら、彼らはどのようなことが好きで、どのようなことに悩んでいるのかを調べます。例えば「プロテイン」を扱っている場合でも、「減量」「増量」「筋肉」「健康」など様々な視点があり得ます。人が最も求めている情報は、自分の悩みを解決してくれるものです。
③読者を主語にしてメルマガを書く
ターゲットの悩みや嗜好が分かったら、彼らのためになることを大前提にメルマガを書いていきます。大切なのは自分(自社)を主語にしないこと。読者、あるいは第三者を主語にして、役に立つ情報を発信することを忘れません。
宣伝告知と情報の比率
とはいえ、メディアとしてメルマガを配信していく中でも、どうしても商品のご案内をしたいときが出てきます。
商品の宣伝と、メディアとしての情報発信の理想的な比率は2:8です。週に1回メディアとしての定期的なメルマガ配信をしながら、月に1回程度であれば商品の宣伝告知も許容範囲です。バランスを見ながら調整してください。
メディアとしてのメルマガのもう1つのメリット
実は、メルマガをメディアとして捉えると、もう1つ良いことがあります。それはネタ切れしにくいことです。
自社の商品をPRすることだけを目的にしていると、すぐにネタがきれてしまいます。しかし、メディアとして捉えるとお客様の悩みを解決する方法、業界の最新情報、AとBの比較など様々なバリエーションが考えられるようになります。
先ほど、「プロテイン」を例に出しましたので、そのまま同じ例で考えてみます。
●自社の商品PRをしようとしている場合
・プロテインの成分
・どんな場面で使えるのか
・プロテインの効果的な飲み方
・他社のプロテインとどう違うのか
・新商品のご案内
などがテーマとして挙がるでしょう。
●メディアとしてメルマガを配信する場合
(主なお悩みを「筋トレ」と定義)
・筋トレとプロテインの相乗効果
・最新マシンの紹介
・筋トレに最適な時間は?
・この夏鍛えるべき筋肉はココだ!
・今、女子が注目する筋肉とは?
・部位別の鍛え方 …
などこれ以外にも様々なバリエーションが考えられます。
どちらのほうが読まれるかは…言うまでもありませんね。
効果的なメルマガを配信して、お客様との絆を深めていきましょう!